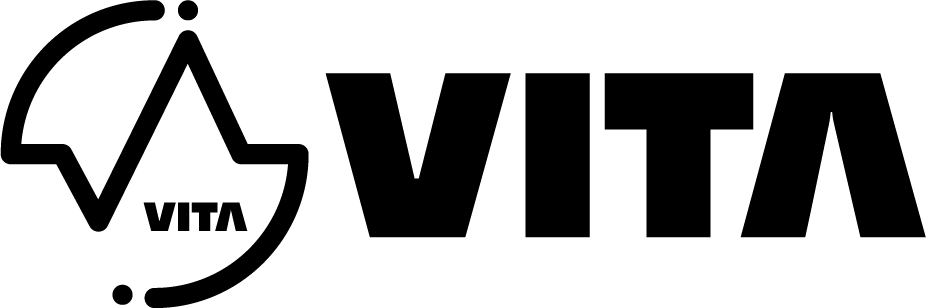【“あの日、大分の空が赤く染まった”】——2025年11月18日・大分県大規模火災が突きつけた“防火管理の現実”——
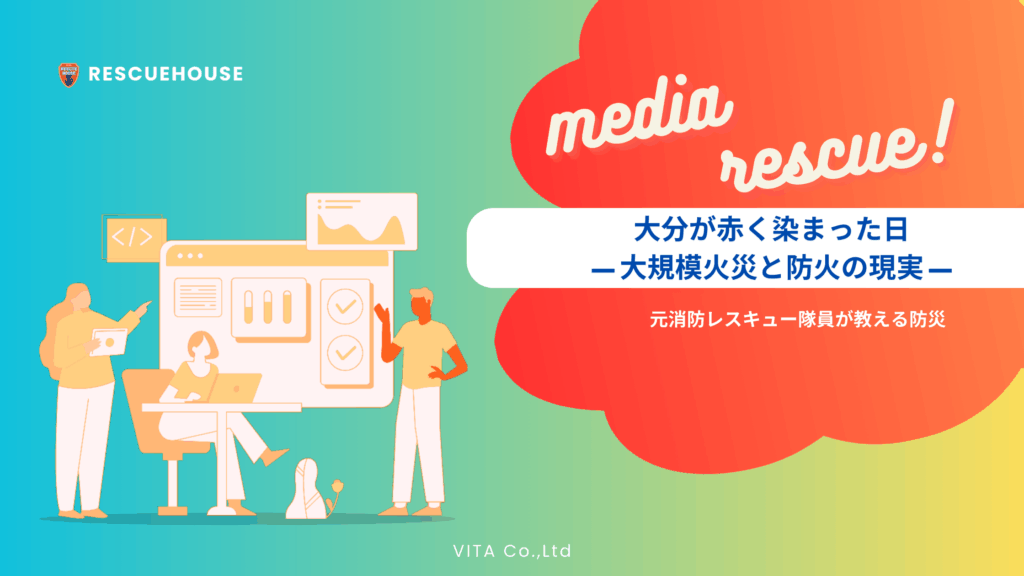
2025年11月18日午後。
晴れた静かな空の下で、誰もが「いつも通りの一日」を送っていた。
——そのはずだった。
14時12分。
大分県内の商業エリアで、最初の通報が入った。
「黒い煙が…!建物の上からものすごい勢いで!」
次の瞬間には“炎の柱”が立ち上がり、隣接する建物の外壁が音を立てて崩れた。
乾いた空気と強めの風。
最悪の条件が重なり、火は生き物のように走り出す。
わずか数分で、街の景色は“赤い色”に塗り替えられていった。

■ 見えてきた“初動の現実”
私は防火管理者として、この日ニュース映像を見ながら背筋が凍った。
「避難誘導は間に合ったのか?」
「火元の管理状態はどうだったのか?」
「なぜここまで延焼が早かったのか?」
火災は原因ではなく、
必ず“準備不足”の結果として起こる。
これは現場で何度も痛感してきた現実だ。
映像を見る限り、最初に燃え広がった建物の裏側には、
可燃物のストックやダンボールが積み上げられていた形跡。
さらに、換気設備の油汚れが炎を“加速させた”可能性も高い。
火は「弱いところ」を突いてくる。
そしてそれは、多くの場合——
人が“危険と気づかなかった場所”だ。
■ 逃げ惑う人々。その裏側にある“3つの盲点”
火災現場の映像には、
避難が遅れて煙の中を走る人の姿が映っていた。
① 炎より先に「煙」が襲う
黒煙は2〜3回吸い込むだけで、正常な判断を奪う。
火より先に人の命を奪うのは“煙”だ。
② 非常口の位置を知らない
普段から確認していないと、火災時には絶対に見つけられない。
非常口は「走って探す場所」ではなく、
平常時に覚えておく場所だ。
③ 初期消火の遅れ
消火器を「使える人」がいなければ、
そこに何本あっても意味がない。
■ 延焼速度が異常だった理由
今回の火災で際立っていたのは、
“延焼の早さ”だ。
その背景には以下のような構造的弱点があった可能性が高い:
-
建物同士の距離が近い
-
外壁材が熱に弱く、火の回りが早い
-
排気ダクトが火を吸い込み“炎の通り道”になった
-
裏側の資材置き場に可燃物が多かった
防火管理者にとってこれらは「見れば分かる危険」だ。
しかし、普段から意識していなければ決して気づけない。
■ “炎は見てから逃げる”では遅い
火災の専門家として断言する。
火が見えた時点で、もう半分詰んでいる。
本当の勝負は、煙が出る“前”にある。
今回の火災も、最初の煙に気づいた段階で
すぐに通報し、初期消火が完璧に行われていれば
被害は大きく変わっていたはずだ。
だが現実は——
「大丈夫だろう」
「誰かが消すだろう」
その数十秒の油断が、炎の勢いを加速させる。
■ “防火管理者”という役割の重さを知ってほしい
もしあなたの会社に防火管理者がいるなら、
その人は職場で最も“命の責任”を背負っている存在だ。
-
点検が形骸化していないか
-
可燃物は溜まっていないか
-
避難訓練が形だけになっていないか
-
消火器は誰でも使える状態か
-
電気系統の異常は放置されていないか
これらを見ているのが、防火管理者だ。
だが現実には、
本業の片手間、研修だけ受けた“名ばかり管理者”が多い。
今回の火災は、
「もし自分の会社ならどうなる?」
この問いを、私たちに突きつけている。
■ ——そして、街は黒い煙に包まれた
あの日、大分県の空を覆ったあの煙は、
ただの煙ではない。
「人が見落とした危険の集まり」だ。
火災は天災ではない。
ほとんどが“防げる人災”だ。
そしてその最前線に立つのが、
防火管理者という存在であり、
その一つひとつの行動が“街の未来”を守る。
■ 最後に
2025年11月18日の大分県大規模火災。
これは他人事ではない。
明日、あなたの会社でも起こり得る。
だからこそ今日言いたい。
「防火管理は、誰か一人の仕事じゃない。
“そこにいる全員の命”が協力しなければ守れない。」
火は一瞬で日常を奪う。
だが、備えは“今日からすぐに”できる。
もし防火管理者のなり手がいない、防火管理者を専門家に任せたいという方は下記の問い合わせまでご連絡をお願いいたします。
防火管理担当:info@bosai-vita.jp
 夜間火災は死亡率が昼の2倍以上
夜間火災は死亡率が昼の2倍以上人が寝ていて発見が遅れる。
住宅用火災警報器は“寝室”に必須。