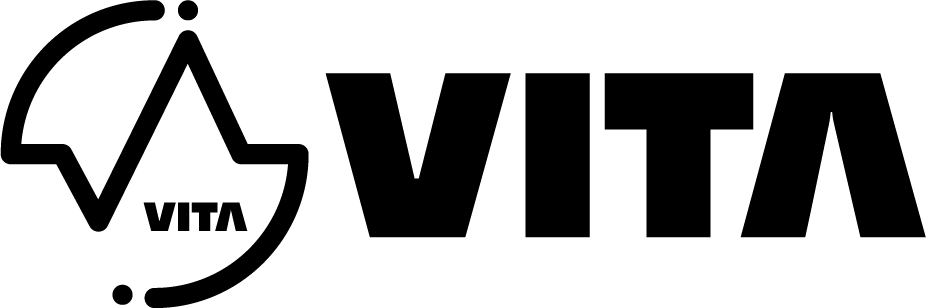【静かな秋、燃え上がる現実】―企業を襲う“見えない火種”の正体―
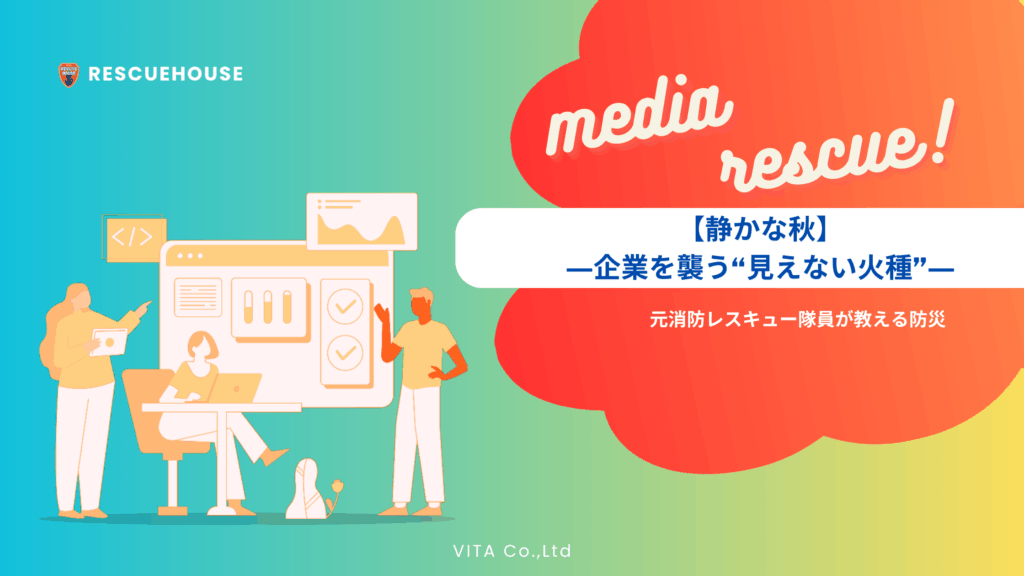
秋。
空気が澄み、風が心地よく感じる季節――。
だが、消防の現場ではこの季節を「火災の季節」と呼ぶ。
乾いた空気。
古くなった暖房器具。
そして「まだ大丈夫だろう」という油断。
その全てが、会社や店舗を一瞬で灰に変える引き金になる。

■実際に起きた“秋の火災”
東京都内のあるオフィスビル。
昼休み、社員が給湯室で鍋を温めようと電気コンロを使用。
ほんの数分、電話の対応でその場を離れた――。
戻った時には、白い煙が天井を覆い、火が壁を這い上がっていた。
火元は、近くに置かれていた紙資料の山。
「燃えるとは思っていなかった」と担当者は言う。
しかし、火はわずか5分でフロア全体を黒煙に包み、約2,000万円の被害。
幸い人的被害はなかったが、会社の営業は3週間停止した。
「まさか自分たちが」――
火災に遭ったすべての人が、そう口を揃える。
■秋が“危険”な理由
- 湿度40%以下になると、火の粉は驚くほど早く広がる。
- 暖房機器の試運転時は、ホコリや可燃物が火種になる。
- 衣類、書類、紙箱などが密集したオフィスや店舗は“燃えやすい空間”。
一度燃え広がれば、スプリンクラーが作動する前にフロアが炎に包まれることも珍しくない。
■火を止められるのは、“意識”だけ
最新の設備を整えても、
人の油断があれば防げない。
たとえば――
・「少しの間だから」と暖房をつけっぱなしにする。
・「後で片づける」と延長コードにほこりをためる。
・「これくらいなら」と避難経路に荷物を置く。
その一つひとつが、炎の引き金になる。
■いま、企業に求められていること
火災は“設備”で防ぐものではなく、“文化”で防ぐもの。
安全への意識を「全社員の共通ルール」にすることが、最大の防火対策だ。
- 定期的な消防訓練・避難訓練
- 防火管理者による点検と啓発
- 「報告しやすい空気」づくり
これらは形式ではなく、“命と会社を守る行動”である。
秋の夜長。
静かなオフィスで光る非常灯を見上げてほしい。
その明かりは、あなたの責任と未来を照らしている。
たった一つの火花で、信頼も、未来も、燃え尽きる。
今こそ、企業として「火に強い文化」を築く時だ。
*レスキュー役立つ豆知識
 落ち葉焼きは「軽犯罪法違反」になることも
落ち葉焼きは「軽犯罪法違反」になることも煙や火の粉で延焼すれば、罰金や責任を問われる可能性があるので注意⚠️